マイクラ(Java版)のコマンドで動物とトロッコをレール上の同じ場所に召喚すると動物はトロッコに乗ってレールを動いてくれる。ただ動物の向きを進行方向にするのは毎ティック、tpコマンドを使ってる。 #Minecraft pic.twitter.com/bnGWVRzdj2
— Yamaguchi Tatsuya (@yt) September 8, 2021
マインクラフトの世界で広大な移動やアイテム輸送を実現するトロッコ鉄道は、冒険を進める上で非常に便利な設備ですよね。
しかし、いざ線路を敷こうとすると、「設置したレールの向きが意図せず横になってしまう」「パワードレールでどう方向転換させたらいいのか分からない」「上り坂で減速させない置き方は?」など、「マイクラレール向き」に関する多くの疑問に直面することがあるかと思います。
この記事では、4種類のレールが持つ特性や、レールの正しい置き方、効率的な加速間隔、そして自動化に必要な方向転換や分岐の仕組みまでを、具体的な疑問に答える形で詳しく解説していきます。
基本的なレールの作り方から、意図しない接続を防ぐコツまで、あなたの理想の鉄道システムを構築するために必要なすべての情報をご紹介します。さあ、一緒に快適なマイクラ鉄道ライフを始めましょう。
- 4種類のレールがあり、カーブできるのは通常のレールだけである
- 平地で最高の加速効果を得るには、38ブロック間隔でパワードレールを配置する
- レールが隣の線路と繋げたくない時は、設置順序や長さを調整する工夫が有効
- ディテクターレールやアクティベーターレールを利用し、自動発車や方向転換を制御できる
マイクラのレール向きを理解する!基本の置き方と種類
- レールの種類と作り方(レールが持つ向きの特性)
- カーブの仕組みと方向転換の方法
- 意図しない接続を防ぐ!レールが繋げたくない時の向き調整
- トロッコの進行方向を決定づける分岐点の切り替え方
- 廃坑利用のススメとレールの効率的な作り方
レールの種類と作り方(レールが持つ向きの特性)
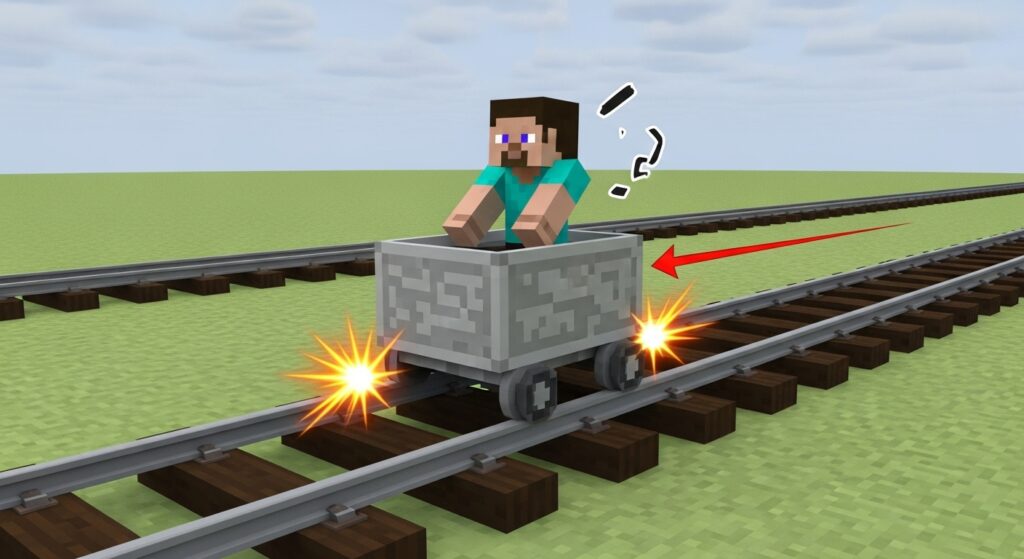
マイクラのレールシステムを理解する上で、まず把握しておきたいのがレールの種類と、それぞれが持つ「向き」に関する特性です。レールは全部で4種類あり、それぞれ役割が全く異なります。
一つ目は最も基本的な「レール(通常)」です。
鉄インゴット6個と棒1個から一度に16個クラフトでき、資材効率が非常に良いのが特徴です。このレールは、直線、カーブ、分岐、坂道にすべて対応しており、線路の「向き」を柔軟に決めることができる唯一のレールです。
二つ目は「パワードレール(加速レール)」です。
長距離移動や坂道でトロッコを加速させるために必須のレールで、金インゴット6個、棒1個、レッドストーンダスト1個で6個作れます。
レッドストーン信号がONであれば加速し、OFFであれば減速・停止します。重要な点として、パワードレールはカーブさせることができません。
常に直線か坂道の「向き」にしか設置できないため、曲がり角には通常のレールを使わなければならないことを覚えておきましょう。
三つ目は「ディテクターレール(感知レール)」です。
トロッコが上を通るとレッドストーン信号を出力する感知系レールで、自動駅や分岐制御に使用されます。レシピは鉄インゴット6個、石の感圧板1個、レッドストーンダスト1個で6個作成可能です。これもまた、パワードレールと同様にカーブはできず、直線的な「向き」にしか置けません。
四つ目は「アクティベーターレール(起動レール)」です。
動力がONの状態でトロッコが通過すると、搭乗者を強制下車させたり、TNTトロッコを起爆させたりするなど、特殊な動作を実行させます。鉄インゴット6個、棒2個、レッドストーントーチ1個で6個クラフトできます。こちらも「曲げ方」の特性は無く、直線的な「向き」に限定されます。
これら4種類のレールの特性を理解し、適切に使い分けることが、スムーズな鉄道建設の鍵となります。
カーブの仕組みと方向転換の方法

トロッコの路線を建設する際、進む方向を変える「カーブ」や「方向転換」は頻繁に必要になります。レールがどの「向き」に曲がるかを理解しておくと、効率的な敷設が可能です。
大前提として、カーブさせることができるのは通常のレールのみであることを再度確認しておきましょう。パワードレール、ディテクターレール、アクティベーターレールは曲がりませんので、曲がり角では必ず通常のレールに切り替える必要があります。
通常のレールを敷く際、レールは自動で周囲の状況を判断し、隣接するレールやブロックと接続してカーブした「向き」に変化します。進みたい方向のブロックにレールを置くだけで、自動的に適切なカーブの「向き」になるため、設置自体は非常に簡単です。もし、意図せず曲がってしまった場合は、一度レールを破壊して再度設置し直すことで、直線の「向き」に戻すことができます。
また、高低差がある場所で斜めにレールを敷く「斜め設置」についても、隣のブロックにレールを設置することで、自動で斜めの「向き」に接続されます。上りや下りの斜面をスムーズに繋ぐことができるため、地形を問わずレールを敷設する際に役立ちます。
さらに重要なのは、分岐点での方向転換です。通常のレールがT字路のように分岐している場合、そのレールにレッドストーン信号を与えることで、トロッコの進む「向き」を切り替えることができます。この切り替えには、レバーやボタン、あるいは後述するレッドストーン回路を利用します。レバーは信号を継続して送り続けるため、一度切り替えればその「向き」が維持されます。
ただし、トロッコの速度が速すぎると、分岐の切り替えが間に合わないことがあるため、分岐ポイントの手前でパワードレールの配置を調整し、スピードを落としておくのが、安定した方向転換のコツです。
意図しない接続を防ぐ!レールが繋げたくない時の向き調整

「マイクラレール向き」でよくある問題の一つに、隣り合わせに敷いたレール同士が、意図せずカーブして繋がり合ってしまう、という現象があります。特に、自動精錬機などで複数の並行なレールを敷きたい場合、この自動接続機能が厄介になります。
レールは設置時に、周囲の状況に応じて最も適切な「向き」に自動で接続しようとしますが、この挙動は設置する軸(南北軸か東西軸か)によって接続しやすい「向き」が決まっているため、問題が発生しやすい場合があります。
並行するレールライン同士が繋げたくないのに繋がってしまうのを防ぐための基本的な対処法は、レールの設置順番を工夫することです。先にパワードレールを設置してから、それに繋がる通常のレールを配置するなど、意図する接続を先に確定させるように置いていくのがコツです。
また、隣接するレールが意図しない「向き」に接続してしまう場合、少し手間はかかりますが、片方のレールラインをもう一方よりも1レール分長く敷設するという手法が有効です。まず長い方のレールを敷き、その後、短い方のレールを敷設します。これでレールが正しく接続されることが多く、最後に延長した部分のレールやブロックを壊せば、意図した並行な「向き」のレールが残ります。
さらに、レールを一時的に繋げたくない箇所に、看板(サイン)を設置するという方法も、レールの接続を防ぐための工夫として挙げられています。これは、看板がレールの接続を妨げる働きを利用したテクニックです。
レールが思うような「向き」にならない、または不自然に横になるような形で隣のレールに繋がってしまう場合は、設置する軸を変えてみる、または一旦壊して設置の順番や、レールの長さに微調整を加えてみることを試してみてください。この調整こそが、複雑な鉄道網をスムーズに構築するための重要なテクニックの一つと言えます。
トロッコの進行方向を決定づける分岐点の切り替え方

長大な鉄道システムを構築する際、複数の目的地へトロッコを送り分ける「分岐システム」は必須です。この分岐システムは、レールの「方向転換」の特性を最大限に利用して、トロッコの進行方向を決定づけます。
通常のレールは、レッドストーン信号をON/OFFすることで、分岐の「向き」を切り替えることができます。最も簡単なのは、分岐点のレールの横にレバーを設置する方法です。レバー操作一つで、トロッコを左右どちらのルートに進ませるかを選べるようになります。
もし、駅など離れた場所から線路の途中の分岐を切り替えたい場合は、レッドストーン回路を敷設する必要があります。分岐させたいレールの地下に回路とトーチを配置し、その信号をレッドストーンダストやリピーターで駅まで延長します。信号は途中で減衰するため、長距離になるほどリピーターで信号をリフレッシュすることが重要です。
駅側での切り替え操作をボタンで行いたい場合、単なるボタンでは信号が一瞬しか続かないため、出力を保持する仕組みが必要です。一番簡単なのはレバーですが、ボタンを使いたい場合は、T-フリップフロップ回路を使用すると便利です。この回路は、ボタンを押すたびに信号の出力状態(ONとOFF)が反転する仕組みで、一度ボタンを押せば、次に押すまでレールの「向き」が切り替わったまま維持されます。
さらに、ホッパー付きトロッコを使った自動運搬システムでは、ディテクターレールでトロッコの通過を検知し、その信号で分岐を自動で切り替えるシステムも構築可能です。分岐手前にディテクターレールを設置し、その信号でレッドストーン回路を制御し、レール切り替え器を動かすことで、トロッコ通過時に自動で進路変更が行われます。この複雑な「方向転換」の仕組みをマスターすれば、マイクラ鉄道の可能性は大きく広がります。
廃坑利用のススメとレールの効率的な作り方
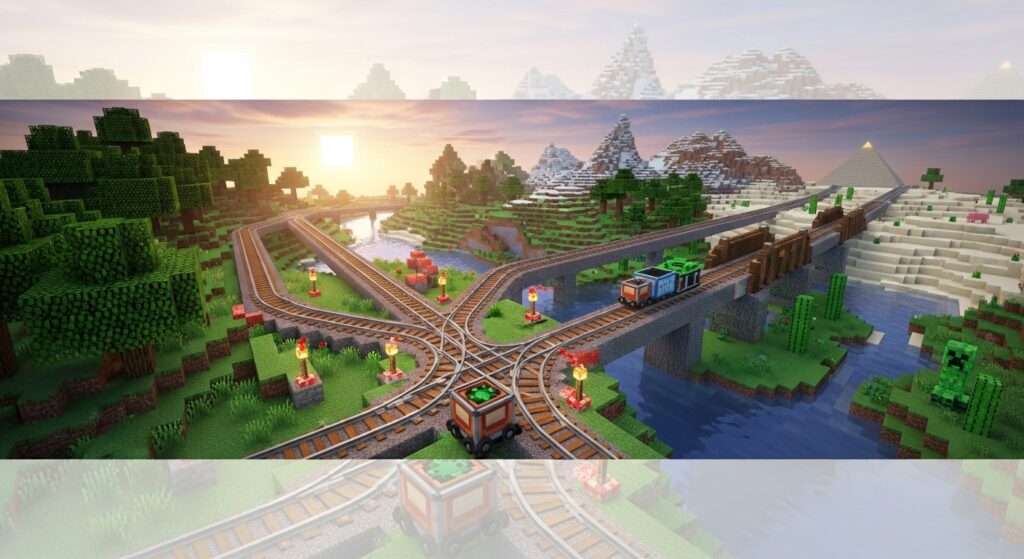
大規模な鉄道システムを作る際に直面するのが、資材、特に鉄インゴットと金インゴットの大量消費です。通常レールを作るには鉄インゴットが、パワードレールを作るには金インゴットが必要ですが、特にパワードレールは金インゴット6個を使うため、長距離を敷設すると膨大な量の金が必要になります。
そこで、効率的なレールの「作り方」と資材調達としておすすめしたいのが、廃坑(廃鉱)の探索です。廃坑は地下深くに自然生成される構造物で、大量のレールが設置された廃線がそのまま残っています。これらの自然生成されたレールをツルハシで回収することで、鉄インゴットの消費を大きく抑えながら、大量のレールを効率的に入手できます。
また、金インゴットの調達については、ネザーでの金鉱石採掘や、ピグリンとの取引が主な方法となります。パワードレールの消費量を抑えるためには、平地での最適間隔(38ブロック間隔)を厳守することが、金インゴットの節約に直結します。
さらに、資材を気にせず大量にレールを敷きたい方、特にJava版プレイヤーには、レール無限増殖装置の利用も視野に入ります。これはスライムブロックやピストンなど、いくつかのレッドストーンコンポーネントを組み合わせた装置で、ゲームのバグを利用してレールアイテムを無限に複製できるというものです。
現行バージョン(2025年9月現在)でも利用可能とされていますが、バグ技であるため、今後のアップデートで修正される可能性はあります。統合版では使用できませんので注意が必要ですが、資材集めの手間を大きく減らすことができるため、大規模な鉄道王国を築きたい方にとっては魅力的な「作り方」の選択肢となるでしょう。
加速と自動化を実現するマイクラレール向きと最適配置
- 減速させないためのパワードレールの間隔と置き方
- 上り坂を最高速度で登るためのレールの向きと配置のコツ
- 自動で発車・停車!ディテクターレールを使った感知の仕組み
- 強制下車やTNT起爆を制御するアクティベーターレールの機能
- 逆走防止策は必須!トロッコの向きを固定する方法
減速させないためのパワードレールの間隔と置き方

トロッコによる移動の快適さは、ひとえにパワードレールの「間隔」と「置き方」にかかっていると言っても過言ではありません。通常のレール上を走るトロッコは時間と共に減速してしまうため、長距離を最高速度(8ブロック/秒)で走り続けるには、パワードレールによる定期的な加速が必要です。
平地でトロッコの最高速度を維持するための最適な間隔は、38ブロック間隔です。これは、普通のレール37個に対してパワードレールを1個配置する構成を繰り返すことを意味します。この間隔であれば、金インゴットの消費を抑えつつ、速度の減衰をほとんど感じさせずに走行が可能です。
もし金インゴットに余裕があり、最高速度をより確実に保証したい場合は、34ブロック以下の間隔で設置すると良いでしょう。
パワードレールを動かすためには動力を供給する必要があり、設置する「置き方」にも工夫が必要です。最も一般的で簡単な方法は、パワードレールの横にレッドストーントーチを刺すことです。トーチを隠したい場合は、レールの真下のブロックにトーチを設置する方法や、レバー、レッドストーンブロックを使用する方法など、さまざまなパターンがあります。動力が供給されている状態のパワードレールは赤く光りますので、設置後に必ず確認しましょう。
また、トロッコが停止した状態からスタートし、最高速度に到達するためには、発車地点に十分な加速を与える必要があります。検証の結果、発車地点にはパワードレールを3つ以上連続して設置することで、瞬時に最高速度に達することができることが分かっています。この初期加速をしっかり確保することで、以降の38ブロック間隔のレールでもスムーズに速度が維持されるようになります。この「置き方」と「間隔」をマスターすれば、どこまでも快適な鉄道旅が実現します。
上り坂を最高速度で登るためのレールの向きと配置のコツ

平地以上にパワードレールの役割が重要になるのが「上り坂」です。トロッコは上り坂では著しく減速し、パワードレールがないとすぐに止まってしまい、逆走の危険さえあります。そのため、上り坂でのパワードレールの「向き」と「配置」は、平地よりも格段に密度を高める必要があります。
上り坂でトロッコの最高速度を維持し、確実に登りきるための最適な間隔は、2ブロック間隔です。これは、通常のレール1個とパワードレール1個を交互に配置する、非常に高密度な「置き方」を意味します。この配置であれば、トロッコは減速を気にすることなく、ぐんぐんと坂を登り切ることができます。
もし資材(金インゴット)の節約を優先したい場合は、3ブロック間隔(通常のレール2個+パワードレール1個)でも最低限の登坂は可能です。ただし、この間隔では最高速度は維持できず、速度は減衰します。長大な坂道の場合は、速度維持のために2ブロック間隔を採用するのが、最終的な快適さに繋がるでしょう。
上り坂でのパワードレールの動力供給も、平地と同様に重要です。スタンダードな「置き方」では、パワードレールの横のブロックにレッドストーントーチを配置しますが、トーチを隠したい場合は、パワードレールが設置されたブロックと、その下のブロック、さらにその下のブロックにトーチを縦に一直線に配置することで、地下から動力を供給し、トーチを隠すことができます。
また、忘れてはならないのが、トロッコが往復する路線の場合、「行きの下り坂」は「帰りの上り坂」になるという点です。したがって、往復システムを構築する際は、下り坂であっても、上り坂と同様にパワードレールを設置しておくことが、スムーズな移動を保証する配置のコツとなります。これにより、長距離かつ高低差のある場所でも、トロッコは問題なく進むことができるのです。
自動で発車・停車!ディテクターレールを使った感知の仕組み
107連かまどです。
— Marks (@Marks_syosetu) October 12, 2021
1ラージチェストの素材を5分50秒ぐらい?で焼けます。
階段状のトロッコ待機エリアを増やすだけで160連かまどまで対応できるかも?
一番下だけ切り替え回路を使って2段目からはディテクターレールでトロッコを感知して上のストッパーを出してます。#マイクラ #自動かまど pic.twitter.com/bg26g72V6s
ディテクターレールは、トロッコが線路上を走っていることを「感知」し、その情報をレッドストーン信号として出力することで、自動化システムに「向き」を与えるレールです。トロッコが上を通過した瞬間、レベル15の信号が出力されます。
この感知の「向き」を利用すれば、さまざまな自動化が可能です。最も一般的なのが、自動駅システムにおける発車・停車制御です。
例えば、自動発車システムを構築する場合、駅の停車位置にディテクターレールを設置します。トロッコが到着してディテクターレールの上に乗ると信号が出力されますが、この信号をリピーターなどで数秒間遅延させた後、発車用のパワードレールに送り込みます。これにより、トロッコは乗降時間を経て自動的に加速・発車するという仕組みが完成します。
また、ディテクターレールは、単なる通過検知だけでなく、積載量の測定という重要な機能も持っています。チェスト付きトロッコやホッパー付きトロッコがディテクターレールの上にあるとき、隣にコンパレーターを設置することで、トロッコ内に積まれたアイテムの数に応じた強さのレッドストーン信号(レベル0〜15)を出力できます。
この機能は、アイテム自動運搬システムにおいて特に強力です。
例えば、採石場などの荷積み駅で、ホッパー付きトロッコにアイテムを積み込んでいる間は停車させ、アイテムが満載になるか、あるいは全て積み終わったら、コンパレーターの信号が変化し、それをトリガーとしてパワードレールをONにして自動で発車させる、という高度な制御が可能です。
ディテクターレールは、トロッコの存在と積載量という情報を正確に捉え、自動システム全体の「向き」を決定づける、非常に賢いレールと言えるでしょう。
強制下車やTNT起爆を制御するアクティベーターレールの機能
流石に階段で昇り降り疲れるから、トロッコ置いた!!
— mii🐈⬛🐾💜 (@r_camellia0220) March 24, 2025
初めてアクティベーターレール使ったよ(゜▽゜)w#マイクラ#マイクラJava #Minecraft pic.twitter.com/YiAuacYPDF
アクティベーターレールは、トロッコに「アクション」を起こさせるための特殊なレールであり、長距離移動のルートの終点や、特定の装置の制御に利用される、非常に特殊な「向き」を持っています。
アクティベーターレールがレッドストーン信号によってONになっている状態でトロッコが通過すると、そのトロッコの種類に応じて異なる効果を発揮します。
一つ目の主要な用途は、搭乗者の強制下車です。プレイヤーやモブが乗っているトロッコがON状態のアクティベーターレールを通過すると、乗客は強制的にトロッコから降ろされます。これは、自動駅で到着後にプレイヤーをトロッコから降ろして停車させるシステムや、トラップで回収したモブを処理層に降ろす際に利用されます。降ろされる「向き」は、アクティベーターレールから見て-X、-Z方向の1ブロック先と決まっています。
二つ目は、TNT付きトロッコの起爆です。TNT付きトロッコがON状態のアクティベーターレールを通過すると、TNTが起動し、しばらくすると爆発します。これにより、遠隔操作での採掘や爆破整地が可能になります。
三つ目は、ホッパー付きトロッコのアイテム回収制御です。ON状態のアクティベーターレールを通過したホッパー付きトロッコは、アイテムの回収を一時的に停止します。OFF状態のレールを通過することで回収を再開するため、特定の区間だけアイテム回収を止めたい場合に有効です。
このように、アクティベーターレールはトロッコの移動そのものを加速・感知するのではなく、乗客や積載物に直接作用するという点で、他のレールとは異なる「向き」の機能を提供しています。高度な自動化や、特殊な装置を構築する際には、このアクティベーターレールの機能が不可欠となります。
逆走防止策は必須!トロッコの向きを固定する方法

鉄道システムを安全に運用するためには、意図しない場所での停止や、特に上り坂でのトロッコの逆走を防ぐ対策が欠かせません。トロッコが一度逆の「向き」に進み始めてしまうと、手動で回収したり、システム全体が混乱したりする原因となります。
最も基本的で簡単な逆走防止策は、パワードレールの後方(トロッコが進む方向とは逆側)にブロックを設置することです。スタート地点にパワードレールを設置する場合、そのレールが接する進行方向とは逆側の終端にブロックを配置することで、トロッコが進行方向とは逆の「向き」へ進んでしまうのを防ぎ、意図した方向へ確実に押し出すことができます。このブロックがないと、パワードレールで加速しても意図した方向に進まない可能性があるため、設置は必須です。
パワードレールを使わず、通常のレールだけで一方通行の「向き」を固定したい場合は、フェンスゲートを使った応用技が有効です。レールを敷いた窪みの上、またはレールをまたぐ形でブロックやフェンスゲートを特定の場所に設置することで、片方の「向き」から来たトロッコはブロックにぶつかって停車・回収され、もう片方の「向き」から来たトロッコは通り抜けられるように設定できます。
特にフェンスゲートを2つ並べて設置する工夫は非常に便利です。 例えば、特定の「向き」(例:左から右)からの進入は許可し、逆方向からの進入は阻止したい場合、ゲートを操作して一方通行の「向き」を設定できます。フェンスゲートが開いている状態であればどちらからでも通れるため、普段は開けておき、緊急時やトラブル時のみ閉めて逆走を阻止・回収するといった柔軟な運用も可能です。
これらのシンプルな「置き方」の工夫を施すだけで、トロッコの「向き」を固定し、鉄道システム全体の信頼性を大きく向上させることができるでしょう。
総括:マイクラレール向きの極意は4種類のレール特性と最適間隔の理解にある
この記事のまとめです。
- マイクラのレールは通常レール、パワードレール、ディテクターレール、アクティベーターレールの4種類である
- カーブや分岐といった複雑なレールの向きの制御ができるのは通常レールのみだ
- 平地でトロッコを最高速度で走らせるために、パワードレールは普通のレール37個に対して1個(38ブロック間隔)が最も効率的な置き方である
- 上り坂で最高速度を維持するには、普通のレールとパワードレールを交互に置く2ブロック間隔が必要である
- パワードレールに動力を供給するには、レッドストーントーチやレバー、レッドストーンブロックなどを使用し、レールを赤く光らせる必要がある
- 停止状態からスムーズに発車し、最高速度に到達するには、スタート地点にパワードレールを3つ以上連続して設置するのが効果的だ
- レールが隣の線路と意図せず繋がってしまう場合は、設置する順番やレールの長さを調整し、接続の向きを強制的に定めることが重要である
- トロッコの通過を検知し信号を出力するのがディテクターレールであり、自動駅や自動分岐の感知に利用される
- ディテクターレールとコンパレーターを組み合わせることで、ホッパー付きトロッコのアイテム積載量を測定できる
- アクティベーターレールは、動力がONの状態でTNTの起爆やプレイヤーの強制下車など、動作の向きを制御する
- トロッコの進行方向を切り替える分岐点では、レバーまたはT-フリップフロップ回路などのレッドストーン回路でレールの向きを操作できる
- 長距離の分岐制御では、レッドストーンリピーターで信号を延長する必要がある
- トロッコの逆走を防ぎ、進行方向の向きを固定するためには、パワードレールの終端にブロックを置くなどの対策が有効である
- レールの材料を節約したい場合は、地下の廃坑を探索し、自然生成されたレールを回収するのが最も効率的だ
- Java版限定のテクニックだが、レール無限増殖装置を利用すれば、資材の消費を気にせず大規模な鉄道網を敷設できる










